クラウドファンディング
2025.09.12
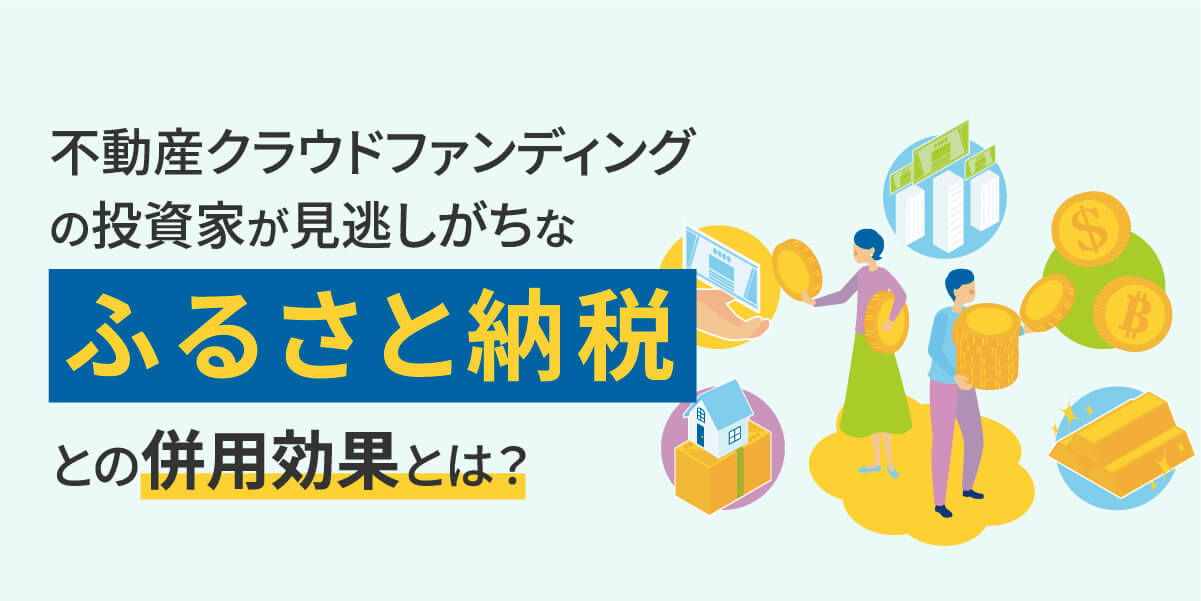
「不動産クラウドファンディングで資産運用しているけれど、税金対策は万全だろうか?」そう考えたことはありませんか? 実は、多くの不動産クラウドファンディング投資家が見逃しがちな「ふるさと納税」との併用が、賢い節税と地域貢献を両立させる秘策となり得ます。この記事では、ふるさと納税の基本から、不動産クラウドファンディングと組み合わせることで得られる具体的なメリット、そして注意点まで、分かりやすく解説します。
この記事の目次
納税と呼ばれてはいますが、実際には都道府県や市町村への寄付のことをふるさと納税といいます。寄付をすることでその御礼として各地方の特産品などをもらえることがあります。この返礼品はふるさと納税額の30%程度が上限とされています。ではなぜふるさと納税が税金対策として注目されるのかというと、ふるさと納税額が翌年の住民税や所得税から寄附金控除として差し引くことができるためです。
一年間に行ったふるさと納税の金額を確定申告やワンストップ特例を利用して申請することで、翌年の住民税や所得税から控除され、支払う税金は安くなります。ただし、2,000円は自己負担額とされています。
たとえば、1年間で5万2千円のふるさと納税をした人で、本来の翌年の税額が50万円だったとしましょう。この場合、翌年の税金は45万円になりますので、ふるさと納税額と合計すると、50万2千円の支出で、本来の税額より2,000円多く支払っていることになります。しかし、5万2千円のふるさと納税の返礼品として1万5千円程度の特産品を受け取ることができるので、お得ですね、という仕組みです。
ふるさと納税で寄附金控除を受ける場合は、原則確定申告が必要です。ただし、もともと確定申告する必要のない給与所得者で、ふるさと納税の寄附先が5自治体以内の人が、きちんと期限内にワンストップ特例の申請書を提出していれば、確定申告をせずに寄附金控除を受けることができます。不動産クラウドファンディング投資家であれば、基本的には確定申告が必要だと考えてください。
個人で不動産クラウドファンディングから収益を得た場合、その収益は『雑所得』として扱われ、原則として確定申告が必要になります。このときに住民税と所得税が発生することになるので、ふるさと納税では、控除上限額内で寄付を行えば、自己負担額2,000円で返礼品を受け取ることができます。
【前提】
総所得金額:800万円
課税所得金額:600万円
ふるさと納税額:17万円(上限約17万円)
この場合、翌年の所得税は3万3千円ほど、住民税は13万5千円ほど軽減されます。
ふるさと納税で17万円支払って、税金が16万8千円軽減されるので、合計では2,000円だけを負担しているという計算です。
上記の例では、2,000円を負担していることになりますが、17万円のふるさと納税により、約5万円相当の返礼品がもらえる可能性があります。不動産投資に限った方法ではありませんが、収入が多いと控除上限額も多くなるため、見落とさず、積極的に活用したい制度です。
不動産投資を行っている人はほぼすべての人が確定申告することになるでしょう。その際に注意すべきなのが、ワンストップ特例申請書を提出した人がそのあとに確定申告した場合、ワンストップ特例は取り消されるということです。忘れずに確定申告書にふるさと納税の内容を記載してください。
また、ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税の対象になります。一時所得には年間50万円までの特別控除額があるので、50万円相当以上の高額な返礼品を受け取った場合などは、それも確定申告する必要があります。
翌年の税金から控除してもらえる金額には上限があり、収入や扶養家族の状況によって変わります。実際には下記の計算式で計算されます。しかし、正確な金額を計算することは難しいので、下記のような様々なポータルサイトなどで公開されている控除上限額シミュレーションを活用して、およその控除上限額を把握することをお勧めします。目安としては、所得金額の2.5%程度になることが多いです。
※ふるさと納税控除上限額シミュレーター
・さとふる
・ふるさとチョイス
・楽天ふるさと納税
・ふるなび
所得税の控除
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
※控除できるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限
住民税の控除(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
※控除できるふるさと納税額は総所得金額等の30%が上限
住民税の控除(特例分)
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)
※住民税所得割額の20%が上限
【追記】
総務省は、2024年6月にふるさと納税の指定基準の見直しを発表しました。
この見直しにより、2025年10月1日からは、寄附者にポイントを付与するポータルサイトを通じた寄付募集が禁止されます。
今まで「寄付+ポイント」というお得さで注目されてきた制度ですが、9月末で最後となります。